 ナマケン
ナマケン
ぼく自身、東京で東日本大震災を経験しました。
ここ数年でも日本のいくつかのエリアで大地震が起こり、Twitterで情報共有もされるようになり、ようやくと自宅の防災対策について意識が向くようになりました。
我が家に子供が誕生したことも大きく影響しています。
そして、いざ準備をしようとすると市販で売られている防災リュックを購入すれば済む話ではないと気づきました。
このページでは我が家の防災対策のはじめの一歩として、どのようなものを準備したのか紹介していきたいと思います。
僕が想定したのは首都直下地震が起こり停電・断水の中での3日間の自宅避難
いざ自宅の防災対策について調べてみたら、いきなり全てに対応した対策は無理だと思いました。
例えば自宅避難か避難所のどちらを想定するかでも、準備しておくべき防災グッズが全く異なってくるからです。
(※例えば避難所に行くことを考えると「タオル、歯ブラシ、エアーマット…」などが必要になり、逆に自宅避難用の水や非常食は不要)
そこで自宅のあるエリアや家の種類から、下記のように被災ケースを想定して、それに見合った対策だけをまずは「はじめの一歩」として取ろうと思いました。
| 考えられるケース | 我が家の場合 | |
|---|---|---|
| 災害の種類 | 大地震、洪水、津波、土砂崩れ、大雪、噴火、竜巻など | 大地震(首都直下型)※政府発表でM7クラスが30年以内に70%の確率で発生 |
| 避難場所 | 自宅避難、避難所 | 自宅避難 |
| ライフライン停止 | 停電、断水、ガス停止、通信回線の混乱 | 停電、断水 |
| 何日間を想定するか | 1日~7日間 | ひとまず最低限の3日間 |
簡単にまとめると、
- 首都直下地震が起こり
- 停電・断水の中で
- 何の支援もない状態で3日間の自宅避難
お住まいのエリア(地震だけでなく洪水や土砂崩れの可能性もあるか)や住んでる家の種類(木造や築年数が古い)によって、上記の被災ケースは異なってくると思います。
また、僕の場合、関東エリアに住んでいるので被災ケースを考える上で「首都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告の概要」を参考にしています。
特に自宅避難と避難所暮らしのどちらを想定するか?
大地震が起こった時にテレビでよく見る光景は避難所が中心になってますよね。
ただよくよく考えたら、全ての人が暮らせるスペースが避難所にあるわけはなく、自宅で生活が可能な大半の方は自宅で避難することになると思います。
東京都で考えると、
- 人口:1,375万人※2018年
- 避難所の収容人数:約328万人※2013年
もちろん全員が入ることになるケースは考えにくく、内閣府「防災情報ページ」の公式発表によると、M7クラスの首都直下地震が起こった場合東京23区だけで49~60万人が避難所に入れない計算となっています。
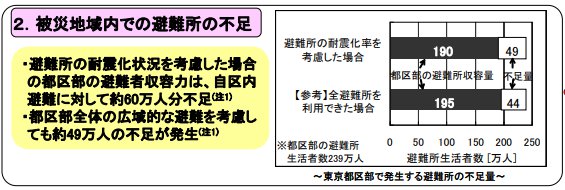
資料:首都直下地震避難対策等専門調査会報告より
有事の際に避難所に入るのは、
- 倒壊や火災によって自宅が被害を受けて暮らせない方
- 理由があって自宅で生活できない方
我が家の場合は自宅がマンションなので、火災にならない限りは自分の家で避難することになると思い自宅避難を中心にして防災対策を考えていくことにしました。
避難所に行くことを想定して「持ち出し用の防災対策」も必要とは思いますが、自宅避難ができない状態になったらせっかく準備していたモノも取り出せない可能性が高いです。
なので最初にやるべき防災対策としては、後回しという判断になりました。
自宅避難用に何を用意したらいいの?ベースとなる備蓄リストを紹介
政府の首相官邸ホームページには、簡単な備蓄リストとして、
- 飲料水:3日分(1人1日3リットルが目安)
- 非常食:3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パンなど
- トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、ろうそく・カセットコンロなど
- ※大規模災害発生時には「1週間分」の備蓄が望ましい
また、東京都防災ホームページから日常備蓄についてまとめられたPDFがダウンロードでき、そこに備蓄品目リストが挙げられています。
※以前配られた「東京防災」という黄色い単行本に載っている情報とほぼ同じ内容
上記を参考に簡単な備蓄リストをまとめてみました。
| 備蓄する物 | |
|---|---|
| 特に役立つもの | 水 カセットコンロ・ボンベ 簡易トイレ 懐中電灯 乾電池 充電式ラジオ 常備薬 |
| 食品 | 主食(無洗米、パックご飯、即席めん等) 缶詰 レトルト食品 飲料 お菓子 |
| 生活用品 | ビニール袋、ゴミ袋 サランラップ テッシュペーパー、トイレットペーパー ウェットティッシュ |
| 女性 | 生理用品 |
| 乳幼児 | 粉ミルク 離乳食 おしり拭き おむつ |
| 高齢者 | 高齢者用食品 補聴器用電池 入歯洗浄剤 |
ただし自宅避難であることを考えると、上記のリストには用意しなくても良い物も混ざっています。
例えばティッシュペーパー、ゴミ袋、ラップ等は備蓄を意識しなくても、たくさん買い溜めしてある家庭も多いですよね。
なのでリストを参考にしつつも、ここから自宅避難用に本当に必要となる防災グッズを揃えていく必要があります。
ローリングストック法はむしろ面倒だと感じた
日常備蓄の方法としては、
- 飲料水
- お米
- レトルト食品
- 缶詰
などを、使った分だけ補充していくローリングストック法が推奨されていることが多いです。
ただ僕は余計に面倒だと感じてしまいました。
例えば飲料水はペットボトルを一度買えば5年間は保存できるものが売られているので5年に1度だけ買い換えれば済みます。
それをローリングストック法で考えると、ペットボトルの水を使っては買うことをずっと続けなくてはなりません。
なので、数年間の長期保存が可能な飲料水やレトルト食品、缶詰などに関しては、最初にまとめ買いして、賞味期限が切れる少し前に消費して買い換える超長期的なローリングストック法の方が楽だと僕は考えました。
 ナマケン
ナマケン
(1)LEDランタン2つ(メイン:単3電池、サブ:手回し充電)
停電になった時、昔は懐中電灯を使っていましたが、今はキャンプ等で使うLEDランタンが便利です。
ランタンにも色々な種類がありますが、防災グッズとして用意するなら乾電池、特に緊急時にも家の中にある可能性が高い単3電池で使えるものがお勧めです。
我が家の場合、単3電池もないケースのことも考えて、
- メイン:単3電池で使えるタイプ
- サブ:手回し充電で使えるタイプ
メイン:単3電池で使える
最初は乾電池も使えて手回し充電も可能な5wayのLEDランタン(amazonや楽天で大量に売られている)を購入しようとしました。
ただ、どうも商品自体の信頼性に欠けると感じてしまい「緊急事態の時に使えなかったら意味がない」と考え有名メーカーのGENTOS(ジェントス)を選びました。
GENTOSのランタンにもいくつか種類がありますが、購入したのは一番明るさが抑えられた100ルーメン(連続点灯12時間)というタイプです。
150⇒280⇒300⇒370⇒380⇒530⇒600ルーメンと数字が大きいほど明るいのですが、
- 同じ単3でも電池の使用本数が多くなる
- 連続点灯時間が短くなる
- 単1や単4乾電池を使うタイプになる
サブ:手回し充電で使える
例えば、メインのランタンをリビング用に使うとして、サブはキッチンでご飯を用意する時などに必要となることを想定しています。
手回し充電できるタイプにした理由は、先ほども書きましたが乾電池が家になかった時のことと、あと万が一、停電が長引いて電池が全てなくなる可能性もあると考えたからです。
手回し機能で一応スマホも充電できるのですが、実験の結果、あまり期待しない方が良いと判断しました。
手回し発電で本当にiPhone充電できるの?停電で困る前に試してみた!
(2)簡易トイレ(コクヨの袋式トイレ30回分)
簡易トイレには大きく2種類あります。
- 組み立ててトイレそのものになるもの
- 自宅の様式トイレに装着させるもの
今回は自宅避難を想定しているので2番目の自宅トイレに装着させるタイプを購入しました。
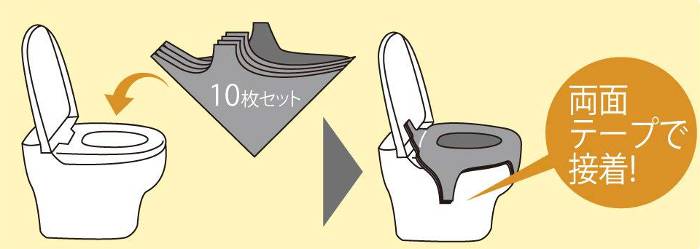
なかなかネットに情報が出てこなかったのですが、これは小だけでなく大にも対応しているタイプなので、断水が起こってもひとまず急場のトイレは凌げます。
(3)飲料水※5年保存
飲料水はローリングストック法ではなく5年間長期保存できるものを買って期限ギリギリまで使わずに置いておくつもりです。
最近では賞味期限が大きく目立つように書かれた防災備蓄用のペットボトルも売られています。
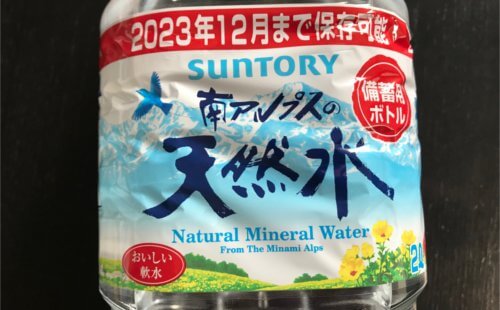
この期限をお使いのスケジュール管理ツール(Googleカレンダーなど)に登録しておけば、5年後にこの水を使って、また5年保存できるものを買い直すだけですね。
この方法なら5年間に1度の手間だけで済むので、やっぱりローリングストック法は面倒だなと感じます。
(4)非常食用のレトルト食品(尾西食品 アルファ米12種類全部セット※5年保存)
非常食も(3)の飲料水と同じ考えで、ローリングストックはせずに5年保存できるものを買ってずっと置いておきます。
Amazonで購入した尾西食品のアルファ米セットは、↓のようにダンボールに保存期間が書かれていたのでとても親切でした。
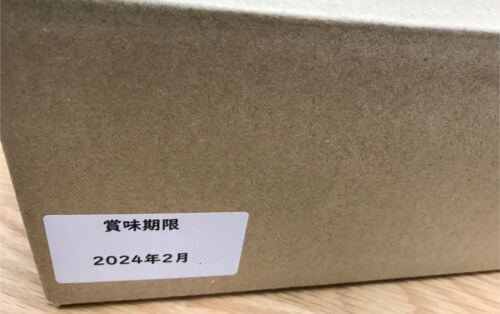
「尾西のアルファ米はまずいの?」と気にされている方が多いので、実際に食べてレビューしました!
非常食「尾西食品のアルファ米」は美味しいのかまずいのか?試しに食べてみた!
レスキューフーズは美味しいけど高いし期限も3年間
美味しいと評判の非常食にレスキューフーズというものがあります。
ただこちらは、
- 1食約918円(尾西食品は291円)
- 保存期間3年(尾西食品は5年)
(5)防災ラジオ(発電[手回し、ソーラー]、スマホ充電も可、ライト付)
ラジオについても乾電池がなくて聞けなかったら意味がないので手回し充電できるタイプを購入しました。
手回しで発電させた電力を、スマホに流して充電できる機能も付いていますが、スマホを充電するには大きな電力が必要なので過度な期待は禁物です。
詳しくは下記ページで実験しています。
手回し発電で本当にiPhone充電できるの?停電で困る前に試してみた!
(6)ソーラーチャージャー(停電が長く続いた時の為に)
もし停電が1週間以上続いたとなると、乾電池もなくなり、電力不足がかなり深刻化してくるはずです。
手回し発電できるランタンやラジオがあってもメインの発電機としては頼りないです。
そこで太陽光で充電できるソーラーチャージャーを購入しました。
これでスマホの充電ができれば、かなり助かるはずと期待しています!
 ナマケン
ナマケン
太陽光で充電できるソーラーモバイルバッテリーが災害(停電)時の助けとなるか試してみた
(7)持ってるから購入してないけどお勧めしたいモノ
モバイルバッテリー
このモバイルバッテリーは僕が週末に出かける時や旅行に行く時は必ず持ち歩いているものです。
20000mAhなのでiPhoneやアンドロイドを約4回フル充電できる優れもの。
さらに1週間くらい放置しておいても放電しづらいというメリットもあるので、地震が来た時にも十分な電力が残っている可能性が高いのもありがたいです!
モバイルバッテリーは本当に便利なので、普段使いとしても緊急用としても1家に1台は持っておくことを個人的にオススメしてます。
余談ですが、僕が男友達へ簡単なお祝いのプレゼントをする時はこのモバイルバッテリーを選ぶことが多いです。
まとめ
 ナマケン
ナマケン
「我が家の防災対策を!」と思って、きちんと情報収集して実際にグッズを購入しながらこの記事を書きました。
ですが、幸いにもまだ本番で試したことがありません。
これからも日々の生活の中で防災情報をアップデートして、不足しているものは追加購入し間違っていたら修正もしていくつもりです。
また、非常用持ち出しバッグについても、今後必要だと思ったタイミングで揃えていきたいなと思います。
その度に、この記事を更新していきますので、ちょくちょく訪問してもらえたら嬉しいです!
![Pursey[パーシー]](https://pursey.jp/wp-content/uploads/2018/01/logo_pursey.png)









